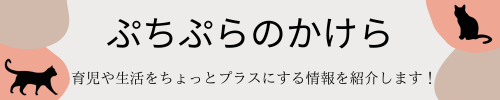松坂桃李さん主演のTBS日曜劇場『御上先生』
文部科学省のエリート官僚が日本の教育現場から権力に立ち向かう「大逆転教育再生ストーリー」が大きな話題を集めています。
センセーショナルな事件をきっかけに、現代における教育や報道の在り方を問題提起として視聴者に投げかける。
今までにない教育ドラマの切り口に、毎週息つく暇もなく見入ってしまいます。
『御上先生』で主演を務める松坂桃李さん。
実は日本アカデミー賞主演男優賞を受賞した映画『新聞記者』でも官僚を務めているんですよね。
松坂桃李さんの『御上先生』がハマり役なので気になって、今更ながら映画『新聞記者』も鑑賞してみました。
そこで今回は御上先生で再注目の映画『新聞記者』とはどんな映画なのか?感想をまじえたオススメポイントをご紹介していきたいと思います。
最後までご覧いただけたら幸いです。
映画『新聞記者』とは

映画『新聞記者』は第43回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞。
最優秀主演男優賞・最優秀主演女優賞とともに3冠に輝いた話題作です。
フィクションとノンフィクションを織りまぜながら、かなり政治的に突っ込んだ内容になっていて、よくこれを映画にできたなと驚きの内容でした。
連日報道されていた「モリカケ問題」
映画『新聞記者』はどちらかというと「加計学園問題」を主題に描かれています。
東京新聞記者・望月衣塑子さんの著書『新聞記者』が原案。
見始めると息つく暇もないほど濃厚なサスペンスに仕上がっています。
映画『新聞記者』あらすじ

日本人の父と韓国人の母の間に生まれた東都新聞社の記者・吉岡エリカ。
ある日、東都新聞社に羊のイラストが添えられた「新設予定の医療系大学に関する極秘情報」が匿名FAXで届く。
通常、大学新設を進めるのは文部科学省主導のはずだが、極秘情報によると今件に関しては「内閣府主導」で新設を進めているとのこと。
しかも新設希望を出しているのは民間経営の大学。
報道に強い使命感を持つ彼女は真相を突き止めるべく、調査に乗り出す。
一方、外務省から出向し内閣情報調査室に勤務する官僚・杉原拓海は、現政権に不利益をもたらす都合の悪いニュースをあらゆる手段でコントロールする任務に葛藤していた。
ある日、杉原は尊敬する外務省時代のかつての上司・神崎と会食をともにする。
楽しい時間を過ごす杉原。
しかし、その数日後、神崎は投身自殺を図るのだった。
5年前の外務省時代、将来を守る約束とひきかえに国のために文章改ざんを命じられた過去をもつ神崎。
実は飛び降りる数カ月前まで、内閣府で大学申請の仕事を任されていたことが判明する。
なぜ神崎は命を投げ出さなければならなかったのか??
1人の記者と1人の官僚の人生が交錯し、浮かび上がる真実とは。
そこには国民生活をも脅かすある計画が隠されていた。
御上先生と同じ脚本家?!
映画『新聞記者』の脚本は第43回日本アカデミー賞で優秀脚本賞を受賞しました。
監督・藤井直人氏、高石明彦氏との共作ですが、そこに名を連ねているのが詩森ろばさん。
詩森(しもり)ろばさんといえば、日曜劇場『御上先生』で大注目の脚本家ですよね‼
リアルな社会問題とフィクションを織り交ぜて生み出される作風に長けていて、『御上先生』でも現代における教育への問題定義を遺憾なく発揮されています。
実は『御上先生』が始動したのも、2020年春に映画『新聞記者』で日本アカデミー賞を受賞した頃だそうですよ。
詩森ろばさんは2025年2月10日配信『FLASH』で以下のように語られています。
たぶん書きたいことはひとつ。
私が伝えたいのは『それでも人は生きていかなくちゃいけないよね』ということ。
人間が生きていること、生きていくために明日につなげていく何かとか。
それを書きたいから、題材がカラフルになっているのかもしれません。
一番大事なのは命。
文化芸術は、命を守るためのものだと思っています」
映画『新聞記者』でも杉原の上司・神崎や、吉岡の父は自らの命を投げ出します。
しかし、杉原も吉岡も二人はそんなに弱い人ではないと信じています。
そうせざるを得ない何かがそこにあったのではないかと真実を探し続ける。
そのうえで、自らも真実に迫ることで苦渋の決断を迫られる。
それでも生きていかなきゃいけない。
詩森ろばさんの強いメッセージは映画『新聞記者』でも発せられています。
映画『新聞記者』の見どころ

映画『新聞記者』は日本アカデミー賞で3冠を受賞した作品です。
フィクションにノンフィクションを練り込んで、重厚感のある作品に仕上がっています。
主演を演じた松坂桃李さんがすごい‼

映画『新聞記者』は実際に問題となっていた「加計学園問題」が物語のベースになっています。
そのため、政権の問題にかなり突っ込んだ内容のため、オファーを受ける女優さんがいなかったという噂も。
『第74回毎日映画コンクール』の日本映画優秀賞受賞の際に、プロデューサーの河村光庸氏はその噂について「全くの嘘です」と否定されました。
ただ、かなり際どい内容なのも事実。
松坂桃李さんも「この作品は完成までに、二転三転、四転…五転して」とコメントを残されています。
そんな中で引き受けた韓国人女優シム・ウンギョンさんはもちろん、日本で活躍しながらもオファーを受けた松坂桃李さんは本当にすごい。
ある意味、政権批判とも取られる内容のため映画に出演するのはかなりの覚悟が必要だったと思います。
その映画を完成させたうえで、日本アカデミー賞受賞の快挙。
映画『新聞記者』で迷いある官僚役を演じた松坂桃李さん。
日曜劇場『御上先生』の官僚→先生の堂々たる演技への系譜に繋がっている気がします。
実在の当事者たちが出演しているのが斬新

映画『新聞記者』には、実際の「加計学園問題」で名前が出てきた方々が出演されています。
原作者の望月衣塑子さん、元文部科学省事務次官前川喜平氏など。
物語に直接関わることはなく、討論番組(?)を放送しているシーンで出演されています。
物語上ではあまり重要ではないのですが、当時の問題をリアルタイムで見ていた身としては興味深かったです。
物語に直接絡めなかったのは、やはり純粋に俳優ではないことと、あまりにリアリティな表現になり過ぎるからですかね(苦笑)
ノンフィクションも織り交ぜた緊迫感に魅せられる

映画『新聞記者』はリアルとフィクションを織り混ぜた社会派サスペンスです。
当時噂されていた与党ネットサポーターを使って、SNSで世論を操作する。
事件の揉み消しを行うなど。
どこまでが真実かは分からないながら、映画では政権の闇も描きます。
「国を守る大事な仕事」の名のもとに、官邸の都合の良い情報を流し続ける内閣府情報調査室。
その仕事に疑問を感じる主人公・杉原は、かつての上司・神崎の死をきっかけに官邸の闇に切り込んでいく。
新聞社に送られてきた匿名FAXを元に、独自に調査を進めていた新聞記者・吉岡。
2人は神崎の葬式の場で出会い、納得のいかない死の真相を探したいという思惑で一致します。
神崎の死の真相には何が隠されていたのか。
映画全面が暗めなライトで、サスペンスのをより深めているのも惹きつけられる要素です。
重苦しいけど、先の展開が気になって思わず見続けてしまいます。
映画『新聞記者』ネタバレなし感想

映画『新聞記者』はじっくりと、それこそドキュメンタリーを追いかけるような感覚で見入るタイプの映画です。
フィクションでありながら加計学園問題を大まかになぞっているので、当時の問題をよく知らなくても分かりやすく作られていると思います。
何が問題だったのか?
どういうことが起きていたのか。
すべてが真実ではないにしても、国民の大きな税金が動いていた問題なので知ることは大事かなと感じました。
こう書くと難しい映画に感じられてしまうかもしれませんが、映画自体は内閣情報調査室を完全に悪として描いているので分かりやすいです。
それこそ悪の組織に立ち向かう(ある種、半沢直樹的な…笑)対立軸がハッキリしたストーリーなので見やすい。
そして家族を犠牲にして身を粉にしながら働く官僚と、その奥さんの姿にも考えさせられるものがあります。
妊婦の妻を持つ主人公の杉原。
杉原の奥さんは官僚の妻という立場を理解して、たとえ自分とお腹の中の子どもが危険な状態にある中でも帰宅しない杉原に怒りをぶつけず…。
出産後も「パパは日本を守ってくれてるんだよ」と子どもに語りかける場面も。
そんな官僚たちに家族がいることを逆手にとって、家族がいるんだろ?と脅しをかける内閣情報調査室。
家族を守るのか?子どもの「未来」を守るのか?
守るものは同じなのに個人を守るのか・国を守るのか究極の選択を迫られ続ける官僚たち。
映画では国を舞台に描かれていますが、民間でもありそうな構図ですよね。
森友学園問題では実際に文章改ざんの事実があったので、そういった選択を迫られることもあったのかもしれません。
結末部分における映画『新聞記者』の問題の真相には賛否両論あると思います。
現実と同じで映画内でも解決には至っていない部分も。
それこそ脚本家・詩森ろばさんの言うところの「それでも生きていかなきゃいけないよね」に繋がるような描写も出てきます。
すべてがスッキリ解決‼終わったぜ!にはなりませんが、全面に緊迫感が溢れていて映画としても見ごたえがありました。
まとめ
御上先生で再注目の映画『新聞記者』とはどんな映画なのか?感想をまじえたオススメポイントをご紹介してきました。
加計学園問題を題材にフィクションを織り交ぜながら描かれる映画『新聞記者』
脚本家が同じこともあり、『御上先生』と同じような重厚な社会派サスペンスを求めている方におススメな作品です。
この機会にぜひ鑑賞してみてはいかがでしょうか?
最後までご覧いただき、ありがとうございました。